先の大阪府知事選・市長選で、大阪都構想を掲げる「大阪維新の会」の松井一郎氏と橋下徹氏が当選したことで、学内外で大阪市立大学と大阪府立大学の統合についての議論が盛んに巻き起こっている。
賛成、反対の如何はひとまず置いておいて、みなさんは本学がそもそもどのような理念によって設立されたのかご存知だろうか。本学には「都市で学び、夢をつかむ」というスローガンがある。また、式辞や入学案内などでも「都市」という言葉が多々使われる。なぜ本学は「都市」という言葉を強調するのか。この記事では、本学の歴史を「理念」という視点から紐解いていく。今後、統合問題について考える機会がより増えるだろう。そのような時に参考にしてもらえれば幸いである。
市大の前身「大阪商科大学」
大阪市立大学の前身にあたる大阪商科大学は、1928年に大阪市立高等商業学校からの昇格という形で設立された。大阪商科大学は日本初の「市立」の大学であった。これには深い理由がある。当時の大学令第五条には「公立大学ハ特別ノ必要アル場合ニ於テ北海道及府県ニ限リ之ヲ設立スルコトヲ得」とあり、「市立」の大学の設立は認められていなかった。つまり大阪市立高等商業学校を大学に昇格させるためには、大学令の改正が必要だったのである。そして、大学への昇格を目指す大阪市や学校の関係者によって、改正へ向けての懸命な働きかけがなされ、晴れて昇格は果たされた。
ただ、この昇格にあたっては文部省の強い反対があった。なぜなら「市立」だと運営の主体は地方自治体であり、国の教育理念と異なる形で運営される恐れがあったためである。事実、国は大学令第一条で、大学の基本的性格を「大学ハ国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授シ並其ノ
関市長の理念
大阪商科大学設立にあたって、大学昇格に大いに貢献した当時の大阪市長・関一氏は「市立商科大学の前途に望む」と題する文を起草し、設立の理念を述べている。
今日世界の大都市、100万200万の人口を有する都市生活には、必ずや不健全なる社会状態が発生しつゝあるもので、之に対してはどうしても神聖なる学問が必要である。 (中略) 従来の古き大学の型を模倣したものでは尚不十分であつて、市民の力を基礎として、市民の生活に最も緊要なる専門的の智識を授くると共に、市民としての一般的教養の機関ではくてはならない。 今や大阪市が市立商科大学を新に開校せんとするに当つて、よく考へねばならぬ事は、単に専門学校の延長を以て甘んじてならぬ事勿論であるが、又国立大学の「コッピー」であってはならぬ。 (中略) 学問の研究が中心であると共に、その設立した都市並に市民の特質と、その大学の内容とが密接なる関係を保つべきことを忘れてはならない。 (中略) 其の所在都市の文化、経済、社会事情に関して、独自の研究が遂げられて、市民生活の指導機関となつて行かねばならぬと思ふのである。
このように関氏は、都市における学問の必要性を説き、大学を都市に必要な精神文化の中心的機関として位置づけた。そして大学は、市民の力を基礎として、市民生活と密着した関係を持ち、指導機関として機能する任務があると論じた。「都市」や「市民」という言葉を多用していることから分かるように、関氏は大阪商科大学設立の依拠となるのは、「国家」ではなく「都市」とした。関氏の掲げた理念は、その後の大阪商科大学及び大阪市立大学のあり方に大きな影響を及ぼすこととなる。
大阪帝国大学との統合案
第二次世界大戦後、学制改革により学校教育法が施行され、戦前の旧制大学は4年制の新制大学として再編されることになる。そのような中、大阪商科大学では新制大学創設をめぐる議論が行われていたが、1947年に大阪帝国大学の総長から、大阪帝国大学と大阪商科大学を統合して新たな総合大学にしないかという申し入れがあった。これに対して、大阪商科大学の教授会では、商科大学は国の支配に左右されることなく、公立として独自の道を進み、その伝統の権威と風格を守るべきだという主張が強く、統合されることはなかった。このように、設立から時が経過しても、大阪商科大学の関係者は、大阪商科大学は公立大学であり、国とは異なった理念で運営されるべき存在だと強く自負していたのだ。
大阪市立大学の発足
1949年、新制大阪市立大学は商学部、経済学部、法文学部、理工学部、家政学部の5学部でもって発足した。開学式の式辞で、当時の大阪市長・近藤博文氏は次のような理念を述べた。
大阪市立大学は大阪カラーの豊かな大学にしたい。同時に大阪市は大学カラーの豊かな、知的な文化都市にしたいというのが本大学設立に込められた願いであります。即ち、本大学は所謂専門的な学識と技能を持ち、実際生活、実際活動に役立つ教養ある市民、良識ある社会人を作ることを目標とするものでなければならないと考えております。
この近藤氏の式辞は、関氏の「大学は都市とともにあり、都市は大学とともにある」という理念を継承したものである。
そして、両市長が掲げた理念は、形あるものとして現在へと受け継がれている。公立大学法人大阪市立大学定款第一章総則・第一条では「この公立大学法人は、優れた人材の育成と真理の探究という大学としての普遍的な使命を果たすとともに、人とその活動が集積する都市を学問創造の場としてとらえ、都市の諸問題に英知を結集して正面から取り組み、その成果を都市と市民に還元することにより、地域社会ひいては国際社会の発展に寄与することを目指す大学を設置し、及び管理することを目的とする」と規定されている。この定款のもと、本学は現在、都市科学分野の研究とシンクタンク機能の充実、高度専門職をめざす社会人の育成、国際力の強化などの施策を推進している。
まとめ
本学の歴史的変遷を、理念という視点から見てきた。本学が「都市」という言葉を強調するのは、このような歴史があったからである。今後、橋下市長が本学と大阪府立大学を統合させようとする際には、「都立」という運営形態にすることに対して、何らかの理念や意義を掲げることだろう。もちろん統合した際のメリット、デメリットを考えた上で賛成、反対を決めるのも一つの方法である。それとは別に、本学の設立理念を知り、今現在その理念は達成できているのかを考えた上で、市長の掲げる理念を比較してみるのも意義深いのではないだろうか。はたして橋下市長はどのような大学論を掲げるのか、私たちは注視する必要がある。
参考文献
大阪市立大学125年史編集委員会『大阪市立大学の125年 -1880~2005- 』大阪市立大学 (2007年)
大阪市立大学百年史編集委員会『大阪市立大学百年史 全学編 上巻』大阪市立大学 (1987年)
高橋寛人『20世紀日本の公立大学 -地域はなぜ大学を必要とするか- 』日本図書センター (2009年)文責
鶴木貴詩 (Hijicho)

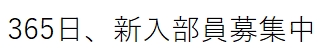




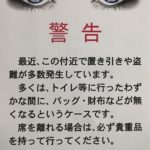


関市長の理念
「市立商科大学の前途に望む」で関市長が述べられた理念の中で私が一番重要と思う部分が欠落しています。それは『大阪市立大学の125年 -1880~2005- 』の161ページ8行目から ”単に商科大学を新設すれば、それで結構だと言ふのではない。市の有機組織の中に編込まれた、別箇のザン(山の下に斬)然特色ある大学、即ち設立した都市の経済生活、及び精神生活と決して離るべからざる関係を有する学問上の中枢機関としての市立大学を新設せなければならぬ。”
関市長は市立大学は市の組織と一体と考えており、都市の経済、精神生活と密接な関係を持ち、学問の中枢機関たるべきものとしているのです。
市立大学は市と距離を置いた別箇の組織とか対峙するような関係などは考えられない訳です。理念から見る市大の歴史ーまとめ の中の一部文言は関市長の理念から外れたものと思われます。
以上
小松俊博