河原で拾ったごみでアートを作る。そんなユニークな活動を行っている市大生がいる。といっても学生団体などの活動ではなく、授業の一環で行っているものだそうだ。
活動は文学部の専門授業で始まったもの。今回は、その中の中村瑠美さん (表現文化・4) 、仲島希さん (哲学・2) 、我有悠生さん (表現文化・2) にお話を伺った。(聞き手:近藤・井坂)

—企画はどのようにはじまりましたか。
活動は「 表現文化演習Ⅱ」という授業で始まりました。25人弱が受講していて、 そのうち、大学外で何かイベントをしようと集まった6人で今の企画(ごみアート)をやっています。
ごみアート以外にもイベント候補はあり、最初は大和川で灯篭流しが提案されました。他にもキューズモールで野外アート・舞島で鬼ごっこなどです。ごみアートは淀川でもやっていたということで、最終的に大和川でのごみアートに落ち着きました。
―授業の流れはどのようなものでしたか。
後期の授業が始まって、しばらくは講義が続きました。11月の後半から計画が始動していますが、外部の方々と交渉するので時間がかかっています。
―これからどのように進めていきたいですか。
淀川ごみアートをやっていた「淀川テクニック」の人にアドバイスをもらう予定です。本当は彼らにも参加して欲しかったんですが、日程が合わずに参加はしていただけませんでした。
まずは、どこにどんなごみがあるかを事前に調べて、ごみマップ作りをします。これを1月の後半に行う予定です。3月にごみ拾いとごみアートづくりを行います。ごみを拾っている間に、ごみの使い道を考えながら拾って、その場でアートを作りたいです。淀川テクニックの人たちは「ごみがごみじゃなく見えてくるのが醍醐味」と言っていました。
―本番では何人規模で実施する予定ですか。
なるべく多くの方とやりたいです。でもアートづくりはあまり人数が多すぎても困るので、人数が多かった場合は小グループに分けて比べ合うということを想定しています。全体の想定では、だいたい20〜50人ぐらいです。
―展示は大和川の河川敷で実施する予定ですか。
管轄の役所の反応は好感触でしたが、越えなければならないハードルが多くあります。3日間ぐらいは展示したいと考えていますが、ただ単に河川敷に展示するだけでは、規模によっては観てもらえないかもしれないので、大学で展示するかもしれません。
―その企画が授業の一貫なのですか。
成績評価の対象になります。役割分担をして、進捗状況を報告しあう授業で、参加度合いで成績認定が行われます。
会議は主に授業時間と、月曜の昼にしています。今後は、大阪芸術大学の学生さんたちの協力も得たいと考えています。というのも、完成度を求めると、専門知識を持っている人が現場に必要なので、芸大の人にナビゲーターとして入って欲しいと思ってるんです。
―継続してこの活動をやっていきたいですか?
かなり地域の人々から歓迎されていてびっくりしました。3月の大和川での本番を契機に、淀川などでもやれたら面白いかな、とは思うんですけど、卒業するメンバーもいるのでどうなるかはわかりません。
文責
近藤龍志 (Hijicho)
関連リンク先
ツイッター:@OcuArts

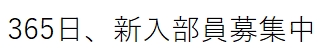







この記事へのコメントはありません。