「市大存亡の危機~無関心ではいられない~」は大阪府市大統合について様々な視点から切り込んでいき、学生の皆さんに問題意識を持ってもらうことを目的としたコーナーである。
今回は平成25年8月27日 (火) に開かれた、第4回大阪府市新大学構想会議にて出された、「新大学案 (素案) 」の内容を見ていく。
「新大学案 (素案) 」
新大学案 (素案) は、平成25年1月18日に大阪府市新大学構想会議から示された「新大学構想<提言>」や、同年4月に出された「新大学ビジョン (案) 」、それに対して行われたパブリックコメントなどをもとに作成されている。
内容は以下のような構成となっている (執筆者要約) 。
第1章 新大学設置の理念
両大学は、これまでも人材の育成と研究成果の還元を通して、大阪の成長に寄与してきたが、統合により、さらに質の高い教育・研究体制を実現させ、世界に対し競争力を持つ新大学として未来に向け新たな責任を果たしていくとしている。そのために新大学は、研究、教育、地域貢献、大学運営において、以下の視点を重視して取り組み、大阪における重要な知的インフラ拠点となることを目指している。
1.研究
地域から世界へ展開し、世界的な研究拠点をめざす
2.教育
地域に根ざし世界に羽ばたく人材を育成する
3.地域貢献
地域社会を創造し、地域活力の源泉となる
4.大学運営
柔軟で持続的に改革する
第2章 理念実現に向けた戦略
1.研究戦略
国立の基幹大学に匹敵する研究活動を推進し、グローバル拠点となることを目指し、同時に地域の課題解決のための研究推進も目指している。また、分野の垣根を越えて異分野融合研を推進することや、国内外の大学・企業・自治体等と連携し、イノベーション創出を推進し、グローバル研究につなげるとしている。
2.教育戦略
教育面においてもグローバル教育 (人材育成) が中心となっている。そのために大阪市立大学 (以下市大) の強みである基礎教育と、大阪府立大学 (以下府大) と学際教育とを掛け合わせ、シナジー効果 (相乗効果) を生み出すことや、全学共通教育 (基幹教育) の充実のために基幹教育機構 (仮称) を設置すること、高度な専門性を有する人材の養成などが掲げられている。
3.地域貢献戦略
産学官連携を通した地域課題の解決や、公開講座の充実など、地域貢献の拠点となること、大阪の産業活性化への貢献、医学部をもつ総合大学の強みを活かし、大阪における健康科学の拠点となることなどが目指されている。
4.運営改革戦略
経営と教学の責任者を分離し、それぞれの一層の充実を図ることや、ガバナンス機能の強化が第一に掲げられている。他に、組織改革のためのPDCAサイクル (改善検証サイクル) の定着、大学独自のブランド力の構築、教員と職員が一体なった「教職恊働」による業務推進体系の構築なども明記されている。
第3章 新大学の教育・研究体制
1.教育・研究体制の基本的方針 (新大学の教育・研究組織図は、素案の24頁を参照)
大きな変化としては、「地球未来理工学部 (仮称) 」の設置と、「人間科学域 (仮称) 」の設置など。その新たな体制のもと、学士課程においては「学部」 (学術的) と「学域」 (学際的) の二つの特徴を最大限活かした教育を目指し、大学院では高度な研究を通じて行う少人数教育により、社会で活躍できる高度専門職業人の要請などを目指している。
また、入試方法の見直しや、実践的教育の充実、教員組織と教育組織を分離したり、アンケート調査等による教育プログラム改善のための戦略等、教育体制の強化、経済支援やキャリア教育の充実、学生生活のサポート等の学生支援の強化なども、掲げられている。
2.全学教育研究組織
全学共通教育を「基幹教育」として学士課程におき、それを統括する組織として「基幹教育機構 (仮称) 」を設置するとしている。
さらに、基幹教育以外にも研究、地域貢献、産学官連携、国際化等の全学教育研究組織を設置するとしている。名称は統一して「推進機構 (仮称) 」とし、高度研究推進機構 (仮称) や国際化推進機構 (仮称) などとする。
3.研究院
教員が効率的かつ円滑に教育研究や地域貢献に従事できるよう、教育組織 (学部・学域・
大学院) とは分離した形で、教員の研究拠点としての「研究院」を置く。
第4章 新大学の運営体制
1.法人と大学の運営方針
理事長と学長はその求められる権限と責任を分離し、理事長は公立大学法人 (以下法人) の長として法人経営を総理し、学長は教学の長として大学運営を総理する、としている。また、法人運営の基本的な取り組みとして、ステークホルダー (利害関係者) との関係構築のため、わかり易い情報開示に努めるとともに、ステークホルダーからの意見集約と反映の仕組を整備することなどがしめされている。そして大学運営の基本的な取り組みとしては、大学運営の課題に対し、トップマネジメントによる迅速な対応を図るため、意思決定のルールを明確化するとともに、教人事権や学長発議の教員採用、学長裁量経費の確保など、トップマネジメントを支える仕組みを構築することなどを示している。
2.教員組織と教員人事
教員組織としては、教育組織との分離のもと「教育院」を設置し、その専門分野に応じて、効率的かつ円滑に教育研究や地域貢献に従事できるようにするとしている。教員の採用、昇任、配置転換等の教員人事は、法人に設置する「人事委員会」が、大学の戦略に合わせて柔軟かつ一元的に行うこととし、学長は、人事委員会の選考に基づき、教員人事の申出を理事長に行うとしている。
3.事務組織
大学の事務組織は、効率化の観点と併せて、大学戦略の推進、教務、入試、学生支援、教育・研究支援といった諸課題への柔軟かつ円滑な対応、組織間の連携強化を図る。また、教員が過度の事務的な業務に煩わされないように、事務機能の効率化を図るとともに、事務職員が、主体的・積極的に参画し、教員と職員が一体となって業務を推進するようにする、「教職恊働」も掲げられている。
第5章 新大学のキャンパス像
当面は現行のキャンパスの有効活用を基本とする (詳しくは素案の18・19頁参照) 。また、キャンパス分散によるデメリットを防ぐため、「キャンパス運営宴楽会議 (仮称) 」を設置し、情報共有を行い、大学としての一体的かつ効率的な運営に努めるとしている。さらに、将来的には、都心への新キャンパス設置等も検討されている。
第6章 その他
1.「新大学案」の取り扱い
新大学案は、公立大学法人の設立団体である大阪府・大阪市が策定した「新大学ビジョン」に基づき、新大学の制度設計や文部科学省による設置認可に向けて必要な基本的事項について、方針などをまとめたものである。
2.スケジュール
今後は以下のようなスケジュールで統合が進められる予定だ。
[平成25年度]
現定款の変更議案の上程 (中期目標の変更、理事長・学長の分離等)
認可申請準備開始 (文部科学省大学設置室 ・各関係省庁)
[平成26年度]
<4月>
新理事長・学長の任命 (理事長・学長の分離)
新大学設置申請書の作成、文部科学省との事務相談等
<5月>
入試科目の公表
<年内>
学内最終手続 (役員会・審議機関等)
<2月>
中期目標の策定、中期計画の策定 (1 法人2 大学に伴うもの)
<3月>
新大学設置認可申請 (文部科学省)
[平成27年度]
<4月>
新中期目標スタート (新法人スタートに伴うもの)
<5月>
大学設置・学校審議会へ諮問
<10月>
新大学設置認可 (見込) 、学生募集・入試 (認可後)
<2月>
中期目標の変更、中期計画の変更 (新大学設立に伴うもの)
[平成28年度]
<4月>
新大学スタート
3.両大学の継続に関する課題
新大学設置後も、現在の両大学の学生が卒業するまで、当然のことながら両大学は存続するものであり、教育・研究の質及び環境は保障する。 特に、歴史・伝統ある両大学を志願された在学生の思いを重く受け止め、大学統合のプロセスの中で、混乱や不信を招くことのないよう、十分な配慮を行う、としている。
参考
大阪府市新大学構想会議
http://www.pref.osaka.jp/shigaku/kousoukaigi/index.html新大学案 (素案)
http://www.pref.osaka.jp/attach/16822/00132205/8%20shiryou3.pdf
文責
橋本啓佑 (Hijicho)

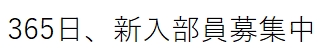







この記事へのコメントはありません。